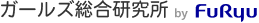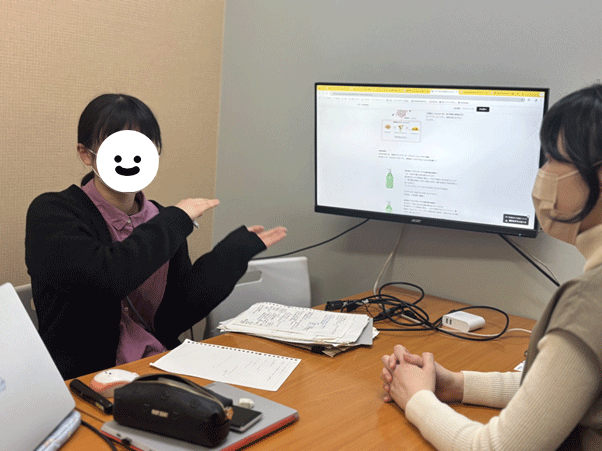ガールズ総合研究所では研究活動の一環として、教育機関のPBL(Project Based Learning:「問題解決型学習」「課題解決型学習」)に協力しております。
企業が抱える実際の課題を題材に、学生さんが解決方法を検討いただくことで参考にするほか、教育機関との新たな共同研究の企画につなげております。また広義には、「未来を切り拓く次世代の応援」としてのサステナビリティ活動の側面も持ちます。
2024年、株式会社CURIO SCHOOOL様が提供する放課後オンラインプログラム「探究ラボ」において、【「推し活をもっと楽しくする探究プロジェクト」】というテーマを提示し、全国から13校が参加いただきました。
この活動の模様の一部は、BSテレ東「THE名門校」でも取り上げていただきました。
当取組の過程で出会った学生のひとりが、「髪」を題材に探求学習を進めている話を聞き、シャンプー・リンスの某大手メーカーの研究員へのヒアリングをセッティングしました。
彼女がなぜこのテーマに興味を持ったのか、現場で働く企業人に出会ったことでどんな着想を得たのか、以下、株式会社CURIO SCHOOOL様が学生・保護者の承諾を受けて執筆した記事を掲載いたします。
<自作のリンスインシャンプーを作るAさん(本人提供)>
「もっと髪をきれいにしたい」——。
そんな思いから始まったのが、岡山県に住むAさんの「髪の毛プロジェクト」です。中学1年生から3年にわたり取り組み続けたこの探究は、自分の髪を美しくするための実験にとどまらず、やがて「地域の魅力を伝える商品づくり」へと進化していきます。
探究の原点は、先輩の後ろ姿
Aさんが「髪の毛」に関心を持ったのは中学1年生の時。
ふと目にした先輩の後ろ姿、ツヤツヤでさらさらと揺れる髪に「私もこんな髪になりたい」と強く思ったことが始まりでした。
それまでは美容にもおしゃれにも関心がなかったAさんでしたが、「自分の髪の毛を最高・最強にしたい」という想いから、本格的な探究がスタートします。
Aさんが掲げた“最高・最強の髪”の条件は次の4つです。
1.ツヤツヤな髪(天使の輪)
2.さらさらな髪(結んでも跡が残らない)
3.まとまりのある髪(はねず、同じ方向を向いている)
4.いいにおいがする髪
⑴生活習慣を変えてみる
まずは、髪をよくするために何ができるかを徹底的に調べました。
雑誌やネット、本などを読み込み、「髪に良い」とされる習慣を6つに絞って、それぞれ1週間ずつ実践してみることにしました。
●髪を洗う前にブラッシングする
●38℃のぬるま湯で1〜3分予洗いする
●コンディショナーを“マスク”のように使用する
●タオルドライで水分をしっかり取る
●洗い流さないトリートメントを使う
●豆腐を中心とした栄養バランスのよい食生活を意識する
特に効果を実感したのは、「髪を洗う前のブラッシング」と「予洗い」でした。
絡まりが減り、泡立ちが良くなったことで、洗髪が楽になり、仕上がりもサラサラになったそうです。頭皮がきれいになることで、髪も自然と美しくなるのではないかという仮説が生まれました。
⑵ベストシャンプーを探す
次に取り組んだのは、「自分に合うシャンプーはどれか?」という問いです。自分にあったシャンプーを使うことで頭皮がさらに綺麗になるのではと思い、市販されているシャンプーを試すことにしました。トライアルセットを活用しながら、25種類以上のシャンプー&トリートメントを同じ条件で試し、マトリクスで評価を整理していきました。
評価項目は以下のとおりです:
●香り
●さらさら感
●ツヤ感
●泡立ち
●まとまり
●洗い上がりの感触
25種類の中でも、特に相性が良いと感じたシャンプーを10種類をボトル買いし、3〜5日間使い続けました。1日ではなく継続して使い続けることで髪にどのような変化があるのか、確かめることが目的です。
試行錯誤の結果、商品Aがもっとも自分に合っているという結論に至りました。プロジェクトを始めたときはシャンプーは高ければ高いほど、効果が高いと思っていたそうです。しかし、数ヶ月試してみて、「高いシャンプー=自分に合うシャンプーではない」と気づきました。そこで、シャンプーは合う、合わないであって値段は関係ないのではないかと考えるようになりました。
加えて、Aさんは、髪の質そのものよりも、香りによってテンションが上がることに気がつきました。シャンプーの良さは、成分だけでなく“気持ち”にも影響することを実感したため、特に相性が良いと感じた商品AのXシリーズを比較することにしました。
⑶商品Aの違いを調べる
さらにAさんは、洗浄力や匂いから、商品AのXシリーズ3製品(保湿タイプ・スムースタイプ・ダメージケアタイプ)に着目しました。それぞれ5日間ずつ使用し、特徴を記録しました。
●保湿タイプ:指通りなめらか。ただし泡立ちが弱く、トリートメント後のべたつきが気になる。
●スムースタイプ:しっとり感が強く、泡立ちも良好。香りが非常に好評。
●ダメージケアタイプ:さらさら感とツヤが優秀。ただし香りが個人的に合わず、継続使用は困難。
同じブランドでも、洗浄後の感触や匂いが全く違うことに気がつきました。製品選びは成分だけでなく、自分の好みや生活スタイルにも密接に関係していると気付いたそうです。
<シャンプー比較を始めたばかり(上)と商品Aのシャンプーを使用した後(下)>
⑷「リンスインシャンプーを自分でつくる」ため、専門家から話を聞く
日々の探究を続ける中で、Aさんが気づいたのは、髪を洗うことの“手間”と“複雑さ”でした。髪をきれいにすることは大切だと思いつつも、毎日のケアが大変で続かないことがありました。そんな矛盾に気づいたAさんは、より気軽に髪を整えられる方法として、リンスインシャンプーを自作しようと決意します。
3月に髪の研究を行うシャンプー・コンディショナーの大手メーカー様の研究員との打ち合わせが実現しました。市販製品の設計背景や、髪の構造に関する知識を教えていただき、探究をする中で生まれた問いに答えを見つけることができました。
<大手メーカー様・研究員(右)にインタビューするAさん(左)>
たとえば:
●ツヤとは何か?
ツヤとは、「髪の繊維方向が整っていることで光が均一に反射される現象」。つまり、髪質だけでなく、光の反射と構造が密接に関係している。
●くせ毛とツヤは関係しているのか?
日本人のくせ毛は繊維方向のばらつきが多く、欧米の“整ったくせ毛”に比べてツヤが出にくい傾向がある。
●シャンプー成分の違いは何か?
シリコンなどの“表面コーティング型”成分は即効性はあるが持続力に欠ける。一方、タンパク質系など“内部浸透型”は継続使用で効果を発揮する。
●性別による「香り」「質感」の違いはあるのか?
○男性:メントール系の爽快感やべたつかない仕上がりを重視。
○女性:ツヤ感、香りの華やかさ、泡立ちや使用時の“幸福感”を重視。
●市販のシャンプーとリンスの組み合わせは最適なのか?
自分に合わせてシャンプーとリンスを組み合わせてもいい。製品ごとの設計が異なるため、「軽めのシャンプー+しっとり系トリートメント」などの使い分けが効果的な場合がある。成分配合のバランスによって、しっとり感とサラサラ感のどちらを重視するかを調整できる。
●髪質や癖毛は遺伝に関係しているのか?
髪質やくせ毛は遺伝的なタンパク質構造に基づく個性でもあり、優性・劣性遺伝による出方の差もある。
研究員の方に聞いた話を元に、Aさんは自作のリンスインシャンプーの検討を始めました。
⑸地域ブランディング × シャンプーを作成する
Aさんは髪の毛を探究する傍ら「この学びを地元に還元したい」と思うようになりました。Aさんが住む新庄村は、岡山県で最も人口の少ない村です。自然は豊かで「日本で最も美しい村」連合にも加盟しています。Aさんは、観光資源としての“体験”が少ないことに課題感を抱いていました。
そこで、黒文字(クロモジ)・米ぬか・ひめのもちなど、村の特産を活かした“ご当地リンスインシャンプー”をつくることを決意します。
クロモジ実験とプロトタイピング
まずは研究員の方のお話を参考に、市販のリンスインシャンプーにクロモジの精油を加え、試作品を作成しました。
<クロモジ精油を入れたシャンプーの試作品(Aさん提供画像)>
試作品を使ってみたところ、香りは引き立ちましたが、洗浄力が落ち、べたつきや頭皮の赤みが出てしまいました。使用量や配合のバランスが原因だと考えられるため、少量のシャンプーではなくボトル等に入れることで、精油とのバランスを検証予定です。
目標は「その場所でしか買えない香りの記憶」を届けるリンスインシャンプーを販売すること。これからもAさんの挑戦は続きます。
探究後インタビュー
Q.探究活動をやってみてどうでしたか?
A:率直な感想としては、髪の毛は終わりが全然見えなかったです。一方で髪の毛が綺麗になったら、生活の質も上がりました。生活が髪の毛に直結してるんだと感じました。ネットや本にある情報は、個人差もあるのか成果が出ないことも多かったので、やはり自分に合うやり方を見つけるしかないと思いました。
Q.これからはどのように探究活動に取り組んでいきたいですか?
A:いろいろ試して効果も分かってきたので、シャンプー作りに専念したいです。目指すのは「ツヤツヤ・サラサラ」。シャンプー作りは組み合わせで効果が変わるので、簡単ではありません。ただ組み合わせることで生じる変化がすごく面白いです。
私はこの探究で、髪の毛は、人を幸せにできることを学びました。その幸せを、私はもっとたくさんの人に届けたいです。
Q.これから探究を始める中高生にどんなことを伝えたいですか
A:「好き」を探究するのが一番だと思います。興味がないものを無理にやっても続かないし、新しい発見への感動もない。
好きだからこそ探究して、より深く学べたり、新しい情報に出会えたりする。今回みたいに「好きなこと」を探究することは大事だなと改めて気づきました。
Q.「好きなこと」を探究する上で大切にしていることはありますか?
A:客観視、ですね。第三者の視点を持つことが重要です。自分の髪の毛で探究しているからこそ、難しいことがたくさんありました。他人のことだったら見えるのに、自分のことだと見えにくい。だから、別の方向から考えるのが大事だと気がつきました。
問題を突き詰めすぎたり、ズレたりしないように、客観視は必要だと思ってます。
Q.「探究はやりたいけど、好きなことが見つからない」という方にはどんなアドバイスをしますか?
A:「日常の困りごと」を見つけてみてください。「これ嫌だな」という感情はいい入り口になります。私も髪の毛のプロジェクトをやりながら、何度も新しい困りごとを見つけて、「これもやりたい!」と思いました。
困りごとは意外と日常の中にたくさんあり、困ってる人も多いです。困りごとを解決することはすごく面白い探究になると思います。
髪の毛から、社会を変える。
「髪の毛は、人を幸せにできる。
その幸せを、私はもっとたくさんの人に届けたい。」
Aさんが語ったこの言葉には、3年間の探究のすべてが込められています。
自分の「好き」や「困りごと」から出発した問いが、社会や地域とつながっていく。
そのプロセスこそが、探究学習の最大の価値であり、未来をつくる原動力なのかもしれません。
※髪質や匂いの感じ方等には個人差があり、上記は全て個人の感想によるものです
本プロジェクトは、株式会社CURIO SCHOOL(キュリオスクール)と協働で実施しました。
株式会社CURIO SCHOOLは「自ら考え、価値を創造する人を増やす。」をミッションに、所属や地域を超えた探究活動をデザインしています。放課後オンラインプログラム「探究ラボ」は、全国の中高生が放課後に自由な探究活動を行うことができるオンライン探究コミュニティです。探究学習を通して中高生が主体的に学びを深める機会を提供しています。
(田中珠里)
今後もこの学びを深めたいというAさんに秘かな期待を寄せるとともに、生活者視点からの問いを立てることと生活者とともに創り上げる重要性を改めて認識いたしました。
この取組がきっかけのひとつとなり、25年夏より株式会社CURIO SCHOOL(キュリオスクール)と協働で行う「エンタメ部」をスタートしました。弊社事業に関する探究学習を学生に行ってもらうもので、随時発信していく予定です。
(林佑樹)
■執筆者:
田中珠里(株式会社 CURIO SCHOOL)
■コーディネーター
林佑樹(フリュー株式会社)